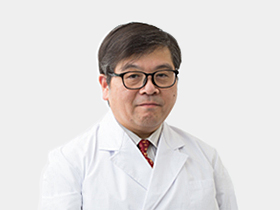医師コラム2022.09.30

不眠は夜間の睡眠が十分とれない症状を指します。なお、「不眠症」と定義され、医療の治療対象となる場合、これに加えて日中に何らかの心身への影響が見られる状態を指します。すなわち、日中への影響がない場合、不眠のみでは厳密にいえば医療の対象にはならず、さまざまな医療外の対処が行われます。このような対処としてはどのようなものがあるのでしょうか。

不眠について最も多い状態とされるものは古く「精神生理性不眠」と呼ばれるものです。これは「今日眠れるかどうか」「明日起きられるかどうか」など睡眠自体がテーマとなって不眠が出現するものです。これらに対してはリラクゼーションの技法が有効です。これらは近年では不眠症治療における認知行動療法の治療パッケージに取り込まれていますが、もちろんリラクゼーション単体でも有効です。リラクゼーションによる不眠への対処の代表格としては自律訓練法とマインドフルネスがあげられ、種々の書籍やホームページにその方法が示されています。
自律訓練法は1932年にドイツで開発された自己催眠技法です。自律訓練法では臥位(ベッド上に仰向けの状態)または座位(椅子に座った状態)の状態で、「気持ちがとても落ち着いている」「手足が重い」「手足が温かい」「心臓が静かに打っている」「呼吸が楽になっている」「お腹が温かい」「額が涼しい」などの自己暗示を各数十分ずつかけて段階的に行っていくものであり、リラクゼーションの目的では最初の3つの自己暗示が用いられます。
マインドフルネスは「現在において起こっている経験に注意を向ける心理的な過程で、瞑想およびその他の訓練を通じて発達させることができる」ものであり、東洋の仏教的な瞑想に由来するとされています。宗教的な高次な内容を対象とするものもあるが、ストレス低減の瞑想エクササイズでは、「息が入ったり出たりする時の感覚」や「音、感覚、思考、感情、動作」に注意を向ける、というものであり、実際に行われることは自律訓練法に非常に類似しています。

コロナウイルスの感染増加でテレワークが増えました。外来に通院している患者さんをみると、通勤に要する時間がゼロとなって浅い睡眠が減少し、睡眠覚醒スケジュールを自分である程度自在に調整できるため、テレワークが睡眠を確保するための恩恵となった人もいる一方で、外出をする機会が激減したため、太陽光にあたることが減ってしまい概日リズムの調整に失敗して睡眠がうまく取れなくなった人も少なくないようです。このように、人の睡眠の調整にあたっては明暗のコントロールは重要な役割を果たしており、テレワークになったからと言って完全に自宅内で過ごすことで問題が起こる人もいるので、本来は日に数時間程度は太陽光のあたる場所に出た方が良いひともいるでしょう。
テレワークの増加がもたらしたもう一つのものは運動量の減少です。不要不急の外出の制限やトレーニング・ジムの利用制限など、一般人口においてはテレワークにより運動量も大きく減少したと思われます。適切なタイミングで行われる適度な運動は、一般的には深睡眠の増加や入眠するまでの時間の減少など睡眠に良い影響を及ぼすとされており、運動量の減少により睡眠は全体として悪化した可能性があります。日中にある程度の運動量を確保することは不眠の一般的対策として有用でしょう。
また、不眠への対処としては、各人それぞれに多くの方法があります。これらの方法はそれぞれの人に一定の効果を有しますが、全ての人に有効なわけではなく、各人にあった方法を見出すことが必要でしょう。
一方、不眠への対処として勧められないものの代表格として連日のアルコール摂取があげられます。連夜のアルコールは睡眠を悪化させるのみならず、場合によってはアルコール依存を引き起こす誘因となるので注意が必要です。