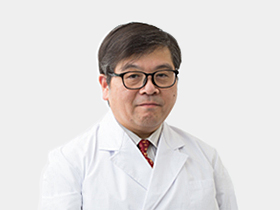医師コラム2022.09.30

朝起きられないことで悩んでいる方は少なくないと思います。睡眠障害の外来でよくみられるのは「目覚ましをいくつかけても目が覚めない」「ご家族が起こしにいって一旦は起きるものの、また眠ってしまい、その後一旦目が覚めたこと自体を覚えていない」「目が覚めても体が動かず、横になった状態から動けない」「一度目が覚めるが、また眠ってしまう」などの訴えです。これらの状態では、「遅刻や欠勤の原因となり、さらには休職や卒業の単位などに影響する」といった明らかな生活障害が出現してしまうことも少なくありません。この問題は現状では「本人の職業意識や根性の問題」とされるのが、社会的な慣行となってしまっています。もちろん、起床行動については本人の“起きるぞ”という意図が重要ではありますが、その背景に「睡眠の病気」が何らかの形で伏在している場合が大部分です。ここでは「朝起きられない」という状態を「起床困難」と称して、お話を続けたいと思います。
さて、このように生活障害を来たす「起床困難」ですが、困ったことに睡眠医学の方でもあまり大きくは取り上げられていません。実のところ、睡眠覚醒移行期の問題について覚醒→睡眠の問題である「不眠症」は睡眠障害の分類としても、一つのカテゴリーとされ、そこでは「不眠」のさまざまな態様が分類され、それに対する対処なども研究されているのですが、睡眠→覚醒の問題である「起床困難」については大きなカテゴリーは作られておらず、この後解説する「概日リズム睡眠障害」の一型として多少取り上げられている程度です。実際のところは「起床困難」には概日リズム睡眠障害だけではなく、背景にその他の睡眠障害や場合によっては精神障害が存在する場合が多いのですが、あまり系統だった分類はされていないのが実情で、我々睡眠障害を診る医師は試行錯誤で対処法を編み出していっている、そんな状況になっています。

さて、朝起きられない原因として最もポピュラーなのが体内時計の問題です。私たちが洞窟の中など、全く外部からの時間の手がかりが得られない場所に置かれると、体内時計のリズムは24時間よりやや長く、24.3から24.7時間程度とされています。すなわち私たちはこのやや長めの周期をもつ体内時計を日照の明暗リズムなどを手掛かりに24時間に同調させているわけです。また、睡眠のメカニズムについては「疲れたから眠る」と「眠る時間になったので眠る」という2つの機構があるとされますが、「概日リズム睡眠障害」では「眠る時間になったから眠る」というメカニズムが非常に強く働いていることがわかっています。このため、睡眠覚醒リズムはもともと24時間より長い体内時計のリズムにひきずられ、眠る時刻も起きる時刻も遅い時間に振れます。このために起床困難が出現するわけです。ちなみに体内時計の指標である深部体温を測定すると、通常の人が夜中の2-4時ころに最低体温が出現するのに対し、リズム障害の人では午前6-8時以降に最低体温が出現します。このこと一つを見ても、こんな体の代謝状態が最低になっている状況で起床行動を行う、ということが非常に難しいことがお分かりかと思います。朝方の不機嫌や起立性調節性障害の低血圧で起きられない、という状態でもおそらくよく似たことが起こっているはずです。概日リズム睡眠障害の起床困難は薬物療法などである程度解決することができます。

起床困難のもう一つの原因が「長時間睡眠」です。長時間睡眠は日中の眠気と大きく関係する状態の一つですが、大体思春期頃から「眠ろうと思えばいくらでも眠ることができる」という睡眠の特徴が見られます。これらの人々の中には起きようとして起きられる人もいるのですが、長時間の睡眠が必要なことから、一般の人と同じ程度の睡眠時間では起きられず起床困難が出現してきます。なお、長時間睡眠の中には、精神的な状態の変化に合わせて睡眠時間が変動する例もあります。
ほか、睡眠の検査をしてみると、通常は入眠直後に出現する深い睡眠が朝の起床直前に出現する人がいて、この場合にも少なからず起床困難が見られます。病態にもよりますが、睡眠を浅くする治療を行うこともあります。