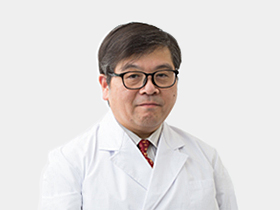医師コラム2022.09.30
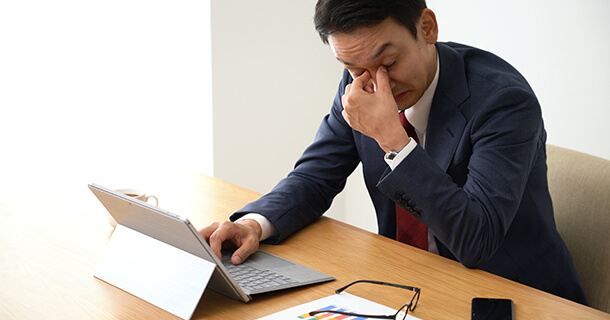
日本は国際的には睡眠時間が最も短い国の1つであることが知られている。OECDの調査では韓国と並んで睡眠時間の短さでは1,2位を占め(OECD)、統計データにもよりますが、その時間は6.6~7.3時間程度でこれはOECDの平均より30分程度も短いとされている。また、この10年程度では全体としては大きな短縮は見られないものの、仕事のある人で大きな短縮が見られている(総務省:社会生活基本調査、NHK:国民生活時間調査など)。
睡眠不足は心身に大きな悪影響をもたらすことが知られている。脳機能への影響としては、睡眠不足により日中の眠気、判断能力の低下、怒りっぽさの増強、会話の理解力と表現力の低下、記憶機能の低下、気分の落ち込み、運動能力の低下などが起こる。これら脳機能への影響は直観的にわかりやすいのだが、近年になって、身体への影響も少なくないことが判明してきた。血圧に対しては、睡眠が良くない人では高血圧になるリスクが睡眠に問題のない人の2倍程度となり、また、人工的に睡眠不足として実験では睡眠不足でない場合と比較して収縮期血圧(いわゆる“上”の血圧)も拡張期血圧(“下”)も明らかに上昇していた。また、不眠が見られた場合、糖尿病に罹患している人の数は健康な人に比較して明らかに多く、1年以上不眠が続いている人では正常な人に比較して2型糖尿病(食生活が大きな原因とされる糖尿病)になるリスクが1.7倍高く、血圧同様に人工的な睡眠不足を作り出すと睡眠不足でない状態よりも明らかに血糖の増加が見られた。ほか、高脂血症についても同様に睡眠不足が影響しているということが知られている。このように、睡眠不足はいわゆる生活習慣病を引き起こす可能性があるのだが、これらの原因として睡眠不足が食欲増加ホルモンであるグレリンを増加させ、食欲減少ホルモンであるレプチンを減少させること、睡眠不足が運動量を減らす、不眠による交感神経刺激によって悪影響がもたらされるということが考えられている。
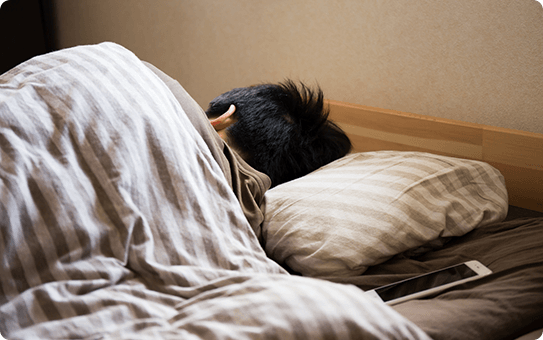
現在、日本の睡眠時間が短時間となっている原因として、労働時間の長さ、IT機器の利用時間の長さ、通勤時間の長さ、などが考えられている。労働時間の増加と睡眠時間の短縮に関係のあることは以前から報告されており、いわゆる働き方改革関連法などでの時間外労働の時間規定に反映され、これらについて数年前から労働基準監督署の監督が厳しくなっていることにお気づきの方もいるであろう。睡眠不足に直接関係したものとしては「勤務間インターバル制度」の創設がある。これは現状では努力義務となっているものであるが、勤務終了と次の勤務開始時刻の間に一定以上の休息時間を設けるもので、EUなどでは11時間の勤務間インターバルが義務づけられている。IT機器の長時間利用については現状では「インターネット依存」として疾病としての対策は厚生労働省を中心に進められているが、社会全体からみた取り組みについては異なった面からの取組が必要と思われる。これに関しH26年度に総務省が出した情報通信白書にてネット依存傾向の国際比較を掲載しているものの、続報となる調査は見当たらず、今後の動向を見守る必要がある。通勤時間と夜間睡眠の関係について、臨床的には睡眠時間の減少のみならず、「翌朝早く起きなければならない」という意識に端を発する睡眠の質の低下が考えられ、実際に睡眠の問題で登校や出社が困難となっている症例で職場や学校近くへの転居などで改善が見られる場合もあった。しかし、研究自体は社会全体を通してのものはなされておらず、2020年に報告がなされているものの、今後施策として検討が必要となるのであろう。
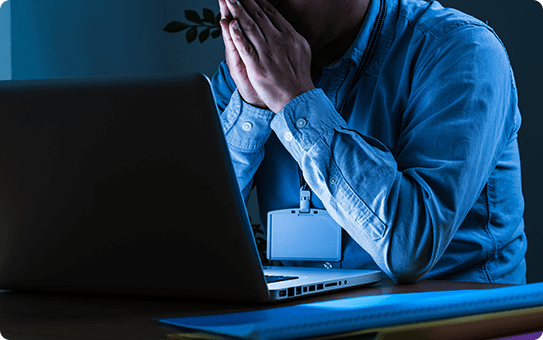
健康日本21とは健康増進法に基づいて2000年に策定された「国民健康づくり運動」で、ここでは種々の健康課題が取り上げられているが、おそらくこの当時には日本人の睡眠時間の減少が問題になりつつあって、健康日本21の健康課題の一つとして「休養・こころの健康づくり」という課題があり、その中で「睡眠による休養を十分とれていない人の減少」などについて数値目標が設定された。目標値は2009年に一度変更され、2022(本)年度に休養を取れていない人が当初の18.4%から15%に減ずるように計画されたが、変動が大きく2018年には21.7%と逆に増加し、さらに2020、2021年度はコロナ禍でデータのサンプリングが中止となっており、最新の結果の発表が期待される。
どうやら我が国の睡眠不足は複数の原因が重なって出現しているようである。この改善のためには、個人の健康管理に追うところも現状では多そうであるが、有効な社会施策を今後考えて行く必要があると思われる。