さまざまな病気が腸と関係していると言われていますが、腸の不調はQOLを下げるだけではなく、健康への悪影響も懸念されます。
「腸活ってどんなことをしたらいいの?」「お通じが良くなるおすすめの方法は?」など腸にまつわる知識を医師に伺いました。
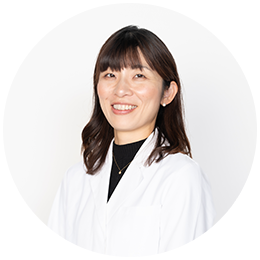
- <飯田先生のプロフィール>
- 飯田 綾子(いいだ あやこ)
2009年奈良県立医科大学卒業。大阪市立大学医学部附属病院で初期臨床研修後、大阪市立総合医療センター消化器内科レジデントを経て、大阪市立大学医学部附属病院肝胆膵内科で学位を取得。
現在は大阪市内のクリニックに勤務し、一般内科外来や在宅診療をメインに行っている。※弊社から飯田先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。
お通じの悪さの原因と改善方法
お通じが悪くなる原因とは?
お通じが悪くなる原因はさまざまありますが、特に食生活や運動習慣の乱れが大きく関係しています。例えば、野菜や果物の摂取が少ないと便が硬くなり、腸の動きが鈍くなることがあります。水分不足や座りがちな生活が続くことでも便が腸内で停滞しやすくなり、お通じがさらに滞ってしまいます。また、ストレスや睡眠不足、不規則な生活習慣も腸の働きを調整する自律神経に影響を及ぼし、腸内環境を乱す要因になります。

お通じの問題を改善するには、お通じが悪くなる理由を理解し食生活や生活習慣を見直すことが大切です。すぐに生活習慣を変えるのは難しいと思いますが、例えば朝起きてすぐにコップ一杯の水を飲むということを心がけるだけでも、腸の動きを活発化させることができます。

便秘の定義と判断基準
慢性便秘症診療ガイドライン2017では、「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」を便秘と定義しています。便秘の状態が続くと便秘症と診断され治療が必要になる場合もあるため、日頃からお通じの状態には注意が必要です。
お通じの悪さの原因
便がスムーズに出ない主な原因は、「腸内での便の硬化」や「腸の動きの鈍化」にあります。
これらを引き起こす主な要因は以下です。
- 食物繊維の不足
野菜や果物、豆類などに含まれる食物繊維は、消化酵素で消化されず大腸に到着します。そこで便の容積を増やすことで腸の蠕動を促します。また、食物繊維は善玉菌のエサになって善玉菌の数を増やす役割があります。これが不足すると、便が硬くなり排便しにくくなります。
- 水分不足
便の多くは水分で構成されています。水分が不足すると便は硬くなりスムーズに移動することができなくなります。
- 運動不足
適度な運動は腸の動きを活性化させますが、身体を動かす頻度が少なかったり、座りがちな生活を送っていると腸の運動が鈍くなります。
- ストレスや
不規則な生活脳と腸は深く関係しています。脳がストレスを受けたり睡眠不足が続いたりすると、自律神経のバランスが崩れ、腸の動きが乱れることがあります。
お通じ改善に効果的なおすすめの食べもの
腸内環境を改善し、お通じを整えるためには、
毎日の食事に効果的な食材を取り入れることがポイントです。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維
水溶性食物繊維は腸内で便に水分を含ませることで便を柔らかくする効果があります。昆布やワカメ、オクラなどに多く含まれています。不溶性食物繊維は便の量を増やし、腸の働きを活発にして排便を促します。ごぼうやニンジン、玄米などがその代表です。食物繊維にも水に溶けるかどうかで2種類あるためバランスよく摂取することが大事と言えます。

海藻類・大麦など

穀物・野菜など
発酵食品と腸内環境の関係性
発酵食品であるヨーグルトや納豆、味噌は腸内の善玉菌を増やし、腸内フローラ(腸内の細菌バランス)を整える効果が期待できます。その他、水分が多い食べ物を摂取することや、食事の時以外でも水を飲むなどをこころがけると便を柔らかく保ち、スムーズな排便を促せます。

整腸剤・便秘薬に頼らずにできる
お通じ改善のためのおすすめの生活習慣
整腸剤や便秘薬は、腸内環境を整えたり、お通じを改善したりすることを目的とした医薬品です。
主に腸内の善玉菌を増やす成分や、腸の働きを調整する成分が含まれており、
一時的なお通じ改善に効果が期待できます。しかし、これらはあくまで補助的な手段であり、
根本的なお通じ改善には、日々の生活習慣を見直すことが欠かせません。
-

日常の生活習慣に
気をつける腸内環境を整えるためには、まず日常の生活習慣に注目することが大切です。適度な運動、例えばウォーキングや軽いストレッチを毎日の習慣にすることで、腸が刺激を受け、自然な排便が促進されます。
-
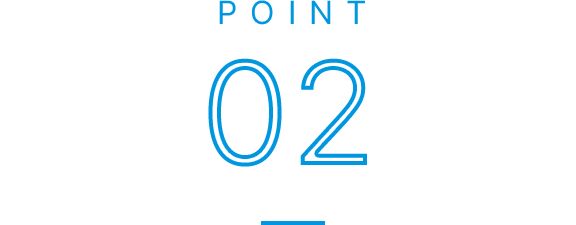
規則正しい生活を
心がける規則正しい生活を心がけ、毎日同じ時間に食事をとり、十分な睡眠を確保することも腸のリズムを整えるために大切です。生活リズムが正しいと腸が「排便の時間」を覚えやすくなり、自然なお通じが促されるようになります。
-
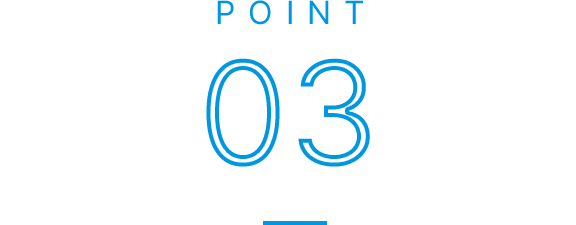
ストレスを
溜め込まない先に述べたように腸は脳の影響も受けてしまうので、湯船に浸かるなどリラックスできる時間を確保し、ストレスを和らげることも、お通じ改善に有効です。
こうした日常生活でのちょっとした工夫を取り入れることで、整腸剤に頼ることなく腸内環境を整えることができます。

※専門家のコメントは商品の推奨及び、商品の効果効能を保証するものではありません。











